 心の旅 山の哲学 行動から思索の世界へ
心の旅 山の哲学 行動から思索の世界へ  心の旅 山の哲学 行動から思索の世界へ 心の旅 山の哲学 行動から思索の世界へ |
|---|
■冬の季節の「知的作業」…2022年 【 認識の哲学 】私たちが「物事を知る」とは、どういうことなのか ( ↓ 2022.03.22 更新) |
|---|
| 山の随想:私の作品集 | 山の文学:私の作品集 | 山の哲学:私の作品集 |
|---|
| |
【 認識の哲学 】 私たちが「物事を知る」とは、どういうことなのか |
報告日 2022.03.22 |
|---|
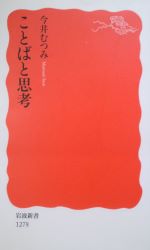  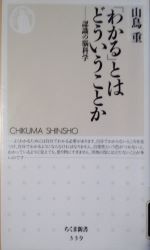 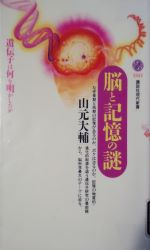   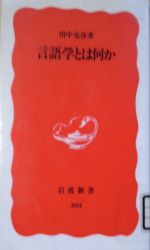 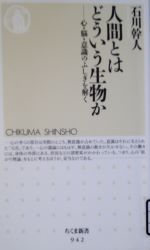  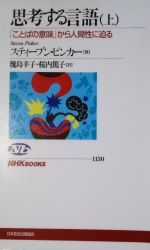  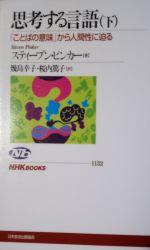 |
●こちら(昭和村)に来て、都会の暮らしから、憧れの「田舎暮らし」を始めた。はじめはこちらの暮らしの環境作り…家屋や敷地の整備…大工仕事や土木作業が中心だった。しばらくして冬の間の過ごし方に工夫が必要なことに気づいた。最初は昭和村の「図書室」に通い、中国史や日本史の本を借りて読んだ…いわば、晴耕雨読の始まり。だが、いい季候のころは、生活にかかわる仕事がかなり多い。長い冬の間の「知的作業」はまとまった「テーマ」に取り組むことができる。そのためには規模の大きい「沼田図書館」にアプローチした。図書館のHPからテーマに即して関連した図書を検索することもできた。PC活用のネットで、アマゾンや「新書マップ」「日本の古本屋」、さらに各出版社のHP検索など駆使してみた。…方法の確立ができた。 ●もともと学生時代の卒論は「カントの認識論」だっただけに・・・人はなぜ「ものごとを認識するのか…認識できるのか」について興味があった。また、これらのテーマについて「思考…考えること」は、自分自身をその実験台にできる、というメリットもある。つまり「自分ならどう考えるの?」と、問いかけられるわけだし、「こう考える」という回答も出せる。…続く ●今回の研究テーマ?は、ずばり「ことばと思考」である。感覚や感情は「ことば」が必要か、「ことば」なしのそれはあるか…、考えることは「ことば」なしでできるのか…いろいろと興味深い。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ■「ことはと思考」 今井むつみ …岩波新書 ● ■「ヒトはなぜことばを使えるか」 山鳥 重 …講談社現代新書 ● ■「わかる ということはどういうことか」 山鳥 重 …ちくま新書 ● ■「脳と記憶の謎」 山元大輔 …講談社現代新書 ● ■「脳からみた心」 山鳥 重 …NHKブックス ● |
|---|
 |
【 山の哲学 】 山への想い:山をもっと広く深く ■ 何故山に登る…私たちの山への素朴な「敬う」という心…未完 |
報告日 2017.01.01 |
|---|
■私は「なぜ、山が好きなのか」そして「なぜ、山に登るのか」と自問自答… ●山・自然への私たちの気持ち=自然崇拝・敬うという気持ち…について色々考えてみたいと思う。私は信心深い方ではない。だが、山頂・山稜での「御来光」に思わず「合掌」してしまう。また、晩秋から初春の山を歩いていて、思いがけず「雪を頂く富士山」に出合うと「拝んで」しまう。何故なのだろうか。これらの私たちの行為や、登山そのものを「信仰」「宗教」の行為とは結びつけがたい。しかし、私たち日本人のの深層心理に、この「山への敬い」と「自然との親しみ」の気持ちが脈々と働いていることは間違いなさそうだ。 ●ここに掲げた図書をざっと読んで、おぼろげながら、学問的に定義された「山岳宗教」が理解できたような気がする。しかし、神道や密教など、OO道、OO教と括られた定義は、私たちには必要のないことで、「山には独特の異気がある。多くの神々の棲家でありながら、また妖怪変化の跋扈するところでもある。そんな妖怪の類は、畏怖心の射出像として誕生したと想像することも可能なわけだが、それは古代人ならずとも納得できそうである。いずれにしても山は物怪たちの饗宴摺る場所であり続けている」と語られる自然感の方が、身近に感じられる。 ●ここに掲げた図書だけでなく、多くは「修験道などの宗教学」「自然崇拝など民俗学」の学術研究書が多く、多少でも哲学をかじった私でも、難解であり、ましてや、ここで求める「山の哲学…何故山に登るのか」の解には程遠い内容であった。ただ、太古の昔の私たちの祖先の自然崇拝の心(DNA)が、現代の私たちの心(DNA)にもしっかり「(潜在意識として)摺り込まれている」ことは、これらの図書から実感することができた。 ●分子生物学的にいえば、私たちのDNAの祖先由来の「自然感受性」の遺伝子が、今、私のなかで突然変異的に「発現=働き始める」のかもしれない…続く。 |
|---|
 |
【 山の哲学 】 山への想い:山をもっと広く深く ■ 何故山に登る…山岳宗教の世界 |
報告日 2011.08.18 |
|---|
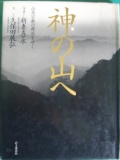 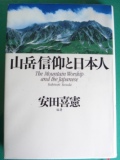 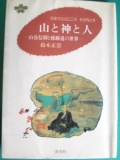  |
●南アルプスの甲斐駒ケ岳を「黒戸尾根」から登ると、麓の「竹宇駒が岳神社」から山頂直下の神社本宮まで、山岳宗教の雰囲気が強く感じられる。新田次郎の「槍ヶ岳開山」を読んだ影響もあり、本格的に「山と宗教」をテーマに、参考書を読み、自分の体験からも「論」を展開してみたい…、と思いつつも時間ばかり経過していく。 ■「山岳信仰」への案内・・・山は神の住まうところ、山は修行の場・空 ●身近なところでは、南アの「甲斐駒ケ岳」は「宗教色」の強い山である。特に北からの「黒戸尾根」はその感が強い。麓の「竹宇駒ケ岳神社」の「奥宮」が甲斐駒の山頂付近にあるり、その途中にもいくつかの「中宮」がある。登山道にも修行を思わせる危険に箇所がある。甲斐駒だけでなく、近場の奥武蔵・奥多摩・奥秩父の山々にも、そこかしこに自然崇拝の形跡がある。山と自然崇拝、修験道などの宗教は切り離せないもののようだ。地元の図書館など手に入りやすい「山岳信仰・宗教」の本を漁ってみた。以下は私が気になった部分の抜粋である。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ■「神の山へ」山岳宗教の源流をゆく…久保田展弘・山と渓谷社 ●「山を歩いていると、風の音にひどく敏感になる。それは風がつりだすさまざまな気配が、山という自然が持っている生命(いのち)の鼓動をいっそう引きだすからだろう」。 ●「日本人が最初に持った宗教を広い意味で神道と呼ぶならば、それは自然への畏敬の念にはじまり、自然崇拝そのものに根差した宗教であったといえるだろう。のちに社ができ拝殿や本殿、奥殿などいくつもの社殿が作られるようになってからも、本来、神社は…ただ拝殿があればそれでよかった。参拝の人々は、拝殿の背後に鎮もる、木立におおわれた山そのものをご神体あるいは神降臨の聖域として仰ぎ礼拝する、これが日本の原初の神信仰であり神道の始まりであった」。 ●「だがなぜ山が神そのものなのだろうか。山にはさまざまな植物が繁茂し、動物や虫が生き、そこに水が流れ、無巨岩が大地を踏まえている。山はこうして生命が渦巻くコスモス(宇宙)であり、生命体そのものであった。山には命の蘇りを可能にする声明エネルギーが充満しているのだ、そしてこの生命エネルギーが燃え立つそこが神の在処(ありか)に他ならなかった」 ■「山岳宗教と日本人」…安田喜憲・NTT出版 ●「なぜ私たち日本人は、山を聖なるものとみなすのだろうか。どうして巨木をみると、注連縄をかけて祈りたくなるのだろうか。どうして御来光をみると、手を合わせて拝むのだろうか。そうした日本人の心の源流は、遠く数千年もの昔にさかのぼる。その一つは縄文の森の心であり、もうひとつは長江文明の稲作漁労民の心である。…。日本人の山と森を崇拝し、太陽を拝む心は、縄文時代以来、数千年にわたって受け継がれきた心なのである。日本人の心の奥底には、縄文時代以来の森の民の心と、弥生時代以来の稲作漁労民の心が、ふつふつと流れているのである。」。 ■「山と神と人」…鈴木正宗・淡交社社 ●「日本の風土の根幹を形成するのは、重畳とと連なる山岳である。山岳は古来から、農耕、狩猟、漁労といった生業の差異を越えて、住民から自然崇拝の対象として崇められてきた。日本の民間信仰の基底には厳しさを持つとともに親しみのある山岳に宗教的意味を与えて尊崇し、それらを対象として宗教的礼儀を行う山岳信仰があり、これを基層文化として、さまざまな信仰形態が作り出されてきたのである。…。山岳信仰の原型は、…火山への怖れ(火山系)、源流地にあって水を司ること(水分系)、死後に人が山に埋葬されること(葬所系)の三つの要素があるという。…」。 ●「この信仰の成立する契機を想定し、①山体の神聖視ないしは、そこに籠る神霊の存在の認知、②生業と関連付けて恩恵的存在と見る態度(農耕民の水分の神、狩猟民の山の獲物の支配神)、③平地民と異なり、特別な力を持つとされる山人への畏怖心が、原始的山岳信仰を形成したとする」。 ■「山岳宗教と民間信仰の研究」(山岳宗教史)…桜井徳太郎・名著出版 ●「日本人が郷土の山によせる思慕畏敬の尋常でなかったことは、多くの詩文が述べている。それを宗教にまで高めたのは神道や仏教、特に修験道であった。したがって日本人の山岳観や山岳信仰は、そうした既成の成立宗教に根ざす山岳宗教の教説が大きく影響している。…。しかしながら、民衆の山岳観や山岳信仰がことごとく既成の志遊興教理や教説に尾を曳くと考えるのは危険である。…」。 ●「峨々たる山岳は山霊の象徴たる山の神の鎮座地であって穢れた俗人の入山を厳重に制禁する。いわゆる不入の聖地である。だから気儘な気持ちで入山登攀するなどもってのほかである。もしもこの禁を破るようなことがあると、山の神の怒りを受けてどんな不祥事が起こらないとも限らない。山は麓にあって遥拝するのみである。そういう観念は、今でも根強く民間信仰として生きている」。 ●「山はまた、死者の霊魂が鎮まり籠る霊地でもあった。それを知らずに分け入った里人が、死霊にあったりいろいろな怪異に遭遇した、という民間説話はいたるところで語られている。この山中他界の観念は、山と日本人とのかかわり方を問題にするときには、決して忘れてはならない領域である。…。民間信仰では、人間が死ぬとその死霊は近くの山に登っていき、そこに鎮座するという考えが濃くみられる。…」。 ●「かつて柳田国男は、民間信仰で観念する祖霊は、仏教などが説くように、十万億土の幽久な彼方へ消え去っていくのではない。現世と交渉を持たない他界へ吸いとられてしまうような存在ではない。…。少なくとも遺族たちの住む近くの山に鎮まっている。そして盆、正月、春秋の彼岸などには、いつも遺族のいる家へ帰ってきて祖霊祭祀の座に連なる。…。このように古来より、日本人の死後観では、…死ねば必ず山に登って行くという感じ方が、いまもなお意識の底に潜伏していると見なければならない。…」。 ●「日本人が山を崇拝した根底には、そこを霊魂のふるさととみる観念があったということだけは否定できない。だから、山は人の近づくことを拒否する凛然たる厳しさがあるとともに、逆に惹き付けて止まない親しさをも持つ。山に対して抱く日本人のこの相反する二つの方向が、実は山岳信仰を今日まで維持してきた原動力であった…」。 ■「山岳宗教」(現代宗教)…佐々木宏幹・春秋社 ●「複雑多様な日本宗教の性格を究明することは、日本研究の魅力的なテーマでもある。中でも、山岳に対する古代からの信仰体系は、さまざまな変遷をとげながら、現代になお大きな意味を持っている。火山や秀麗な山容を誇る名山に対する自然崇拝に発し、次には山中修行の場としての聖なる空間としての山岳が出現する。。そこには神道、仏教、道教、修験道など外来要素と日本の在来要素がミックスされた思想が複合化されて出来上がった山岳宗教の全体像が浮かび上がってくる。」。 |
|---|
 |
【 山の哲学 】 山への想い:山をもっと広く深く ■ 何故山に登る…私たちの祖先・縄文人のDMAが語る |
報告日 2015.00.00 |
|---|
●続く |
|---|
 |
【 山の哲学 】 山への想い:山をもっと広く深く ■ 何故山に登る…著名登山家たちのことば |
報告日 2015.00.00 |
|---|
●続く |
|---|
 |
【 山の哲学 】 山への想い:山をもっと広く深く ■ 何故山に登る…神の山へ…神々の詩…音楽が惹きこむ心の深層 |
報告日 2011.08.20 |
|---|
 姫神…「神々の詩」 |
■姫神…「神々の詩」「風の彼方」 ●今、姫神の「神々の詩」にはまっている。名前はTVの番組の主題曲かなにかで聞いた記憶はあるのだか、図書館からCDをあるだけ借りて、これだけ本気で聞いたのは初めてだ。「山の哲学」で、自然崇拝・山岳宗教に想いを馳せる時を同じくして、偶然にも…というか「神の山へ」の一文…”姫神”の演奏する「ムーンウォーター」という曲を聴いていると…から、私の意識の連鎖が起きた。 ●ある解説によれば…満天の夜空に輝く星、春を告げる雪解けの山鳴り、鳥たちのさえずり、薪が火の中で跳ねる音……姫神を聴いているとこういったイメージがゆっくりと頭の中に溶け出してくる。シンセサイザーという現代的な楽器を使って、自然の鼓動や四季を再現する音楽には、現代人が無くしてしまった何かが、確実に息づいている。そう、それは人が生まれてきたからには、必ずもっているはずの原始の記憶とでもいうべき遺伝子に直接響くような感覚……。縄文人が洞穴の中で聞いたエコー、弥生人が植えた稲が穂をつけ、それが風になびく音、そんな映像が頭の中をフィード・バックしていく。 ●さらに…「姫神」という名前は、岩手県の姫神山に由来するが、81年より活動を続け、現在までにアルバムを20枚以上リリースしている彼は、テクノロジーを使って自然を再生/保護しようとする世の中の動きを確実に先取りしていたといえるのではないだろうか。(リッスンジャパン)…とある。 ■「神の山へ」の世界のBGMが「神々の詩」 ●「山の哲学」の「山岳宗教…神の山へ」(前掲…8月18日)で…「山を歩いていると、風の音にひどく敏感になる。それは風がつくりだすさまざまな気配が、山という自然が持っている生命(いのち)の鼓動をいっそう引きだすからだろう」。…「だがなぜ山が神そのものなのだろうか。山にはさまざまな植物が繁茂し、動物や虫が生き、そこに水が流れ、無巨岩が大地を踏まえている。山はこうして生命が渦巻くコスモス(宇宙)であり、生命体そのものであった。山には命の蘇りを可能にする声明エネルギーが充満しているのだ、そしてこの生命エネルギーが燃え立つそこが神の在処(ありか)に他ならなかった」…という抜粋をここに載せた。この不思議な世界観(存在感と言うべきか)に心を巡らせていると、姫神の「神々の詩」がBGMのように沁みわたってくる。 ●自然を、山を「ことば」で表せば、「神の山へ」で語られていることなのだろう。それを「おと」で表せば、姫神の「神々の詩」やその他の曲が表すものなのだろうと私には思える。歌詞があるわけではなく、歌声も縄文語(?)をモチーフにしているという。歓喜の声や叫び、つぶやきや呻き、に似て意味不明である。それでいて心に深く沁みわたってくる。 |
|
|---|
| 山の随想:私の作品集 | 山の文学:私の作品集 | 山の哲学:私の作品集 |
|---|